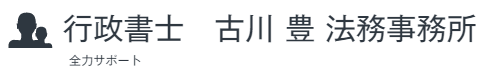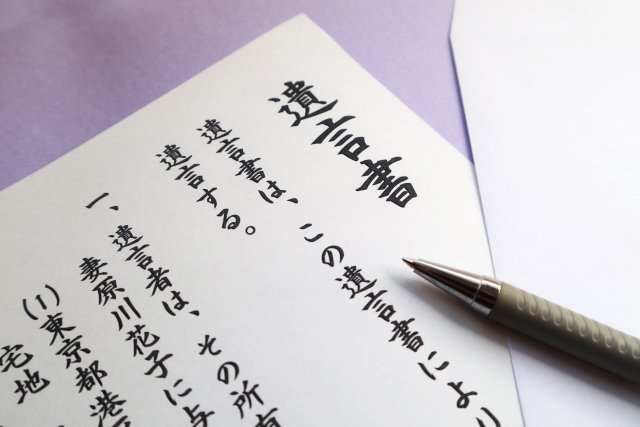代表者 古川 豊
行政書士 古川豊 法務事務所のホームページを閲覧していただきありがとうございます。当事務所では遺言書作成、後見、相続サポートをはじめ、各種許認可申請(農地転用、建設業許可等)、補助金申請サポート、法人設立等、お客様の抱えるお悩みや課題に対して適切な対応を心がけております。また、当事務所では全力サポートを掲げており、時間が許す限りお客様の要望にお応えします。
ゆきまさくんへ相談だ!!

最新記事
- 無料電話相談・メール相談
 お電話での最初の1回30分無料の電話相談を予約制で行っております。またメールでの相談は随時実施中です。 予約制となりますので、お電話かメールにてご確認ください。 📞070-8337-3815 y.furukawa.net […]
お電話での最初の1回30分無料の電話相談を予約制で行っております。またメールでの相談は随時実施中です。 予約制となりますので、お電話かメールにてご確認ください。 📞070-8337-3815 y.furukawa.net […]
お気軽にお問い合わせください。070-8337-3815受付時間 9:00-17:00 [メールは24時間]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください任意後見制度・公正証書遺言ってなに?~終活に備えて~
■任意後見制度とは?
本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。
■今はまだ、元気だから必要ない?
任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。
相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。
(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成
公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。
本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ人に、自分の生活をはじめ、療養看護や財産に関する事務について代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約で決めておく制度です。
■今はまだ、元気だから必要ない?
任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。脳溢血など急な病気で突然、本人の判断力が低下することはよく聞くことですが、認知症になってからだと任意後見制度の対象ではなくなる場合があります。急な入院や葬儀のこと、家の管理など、いざという時に周囲の人々に迷惑をかけないよう、任意後見制度を使い、備える方が増えています。
■公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人や証人の立ち合いのもと、公正証書として遺言書を作成する方法です。
相続手続きの際の家庭裁判所の検認が不要になったり、公証人が遺言書の管理を行ってくれたりと、メリットは断然です。
また、自筆証書遺言ありがちな、遺言が無効となってしまったり、発見されなかったりするリスクをさけることもご本人様の意思が反映される点ではおおきいですね。
(簡単な流れ)
1. 相続人や相続財産を調査する
2.遺言内容(誰に何を相続、遺贈するか)
3.公証役場に連絡して、公証人に遺言内容を伝える
4.公証役場に必要な書類を提出する
5.公証役場行く
6.公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
7.公正証書遺言書の完成
公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要です。
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。