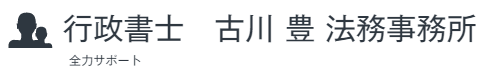業務案内

行政書士のできることは🖊
1.官公庁に提出する書類の作成とその代理、相談業務
2.権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
3.事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
各種許認可申請、契約書、遺言書、遺産分割協議書作成、議事録等の作成・代理・相談を承ります。
ただし、裁判所へ提出する書類、登記申請書、税務署へ提出する税務関係書類、労働保険関係書類などは作成できません。また、紛争性のあるものについてや、税務署への申告、公共性のある測量図面などは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの他士業の独占業務となります。これらに規定されていない役所への提出する書類は行政書士ということになります。よって他の専門家への依頼が必要な場合もあります。お話をお聞きした上で、他の専門家と協力して業務をすすめたり、行政書士が対応しかねる案件ついては、適切な専門家をご紹介させていただきます。それぞれ行政書士法、司法書士法、税理士法、弁護士法にもとづいて誰がどのような業務が出来るかが決まっているためです。そのため、当事務所では他の士業事務所との連携して事案の解決に努めます。
農地転用・開発許可申請をサポートします!

- 農地法第3条許可申請
- 農地法第4条許可申請
- 農地法第5条許可申請
- 農地法第3条届出申請
- 農地法第4条届出申請
- 農地法第5条届出申請
- 農振除外申請
- 開発行為許可申請(第29条)
- 開発行為許可申請(第34条)
- 開発行為許可申請(第43条)
建設業許可申請をサポートします!

- 建設業新規許可(知事免許)
- 建設業新規許可(国土交通大臣免許)
- 建設業各種変更届
- 建設業更新申請(知事免許)
- 建設業更新申請(国土交通大臣免許)
- 建設業決算届
- 業種追加(知事免許)
- 業種追加(国土交通大臣免許)
- 経営状況分析申請
宅建業免許申請をサポートします!

- 宅建業免許申請(知事免許)
- 宅建業免許申請(国交省大臣免許)
- 宅建業免許更新(知事免許)
- 宅建業免許更新(国交省大臣免許)
- 各種変更届他
産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートします!

- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業更新申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 特別産業廃棄物収集運搬業更新申請
飲食店営業許可・風俗営業許可申請等をサポートします!

- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 酒類販売業免許申請
- 風俗営業許可申請
法人設立(起業)をサポートします!
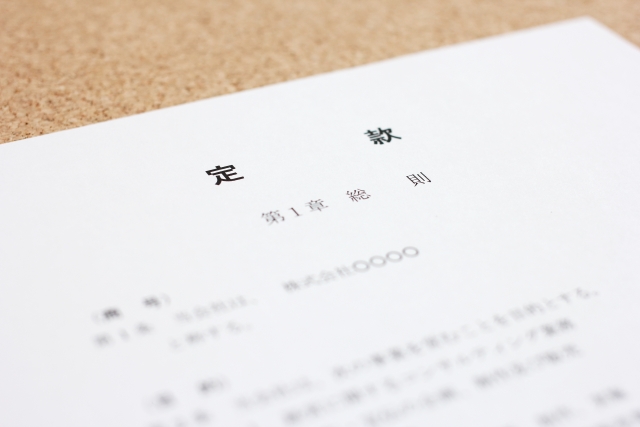
- 株式会社設立
- 合同会社設立
- NPO法人設立
- 電子定款作成認証
- NPO法人年度事業報告書等作成
- 創業支援サービス(融資・補助金)
- 補助金・助成金支援サービス
相続・遺言・家族信託・遺産分割のコンサルティングサポートです!
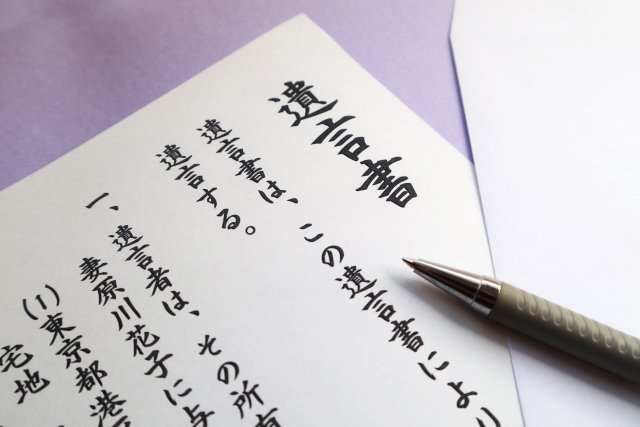
- 家族信託の設計から運用まで
- 自筆証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言作成サポート
- 相続人の調査・確定
- 相続関係図作成
- 法定相続情報証明制度作成申請代行
- 相続財産調査・評価額の算定
- 遺産分割協議書作成
- 遺言執行人(遺言執行手続)
その他のサポート!
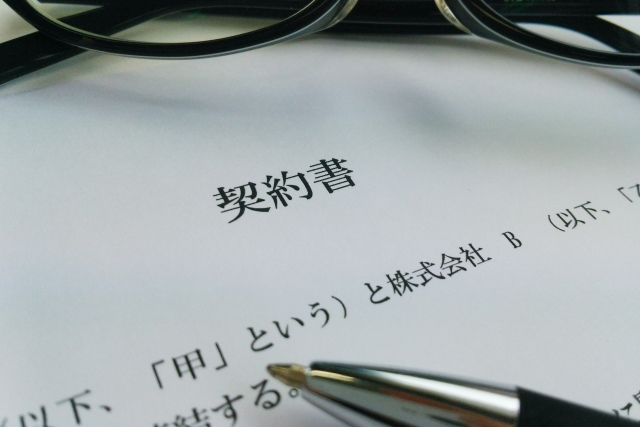
- 各種契約書作成
- 内容証明郵便作成
- 古物商営業許可申請
- 介護タクシー申請
- 特殊車両通行許可申請
- 一般貨物自動車運送業許可
- 特定貨物自動車運送業許可
家族信託(認知症になる前に!!)
家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々