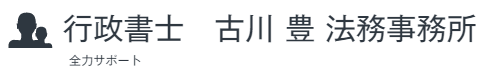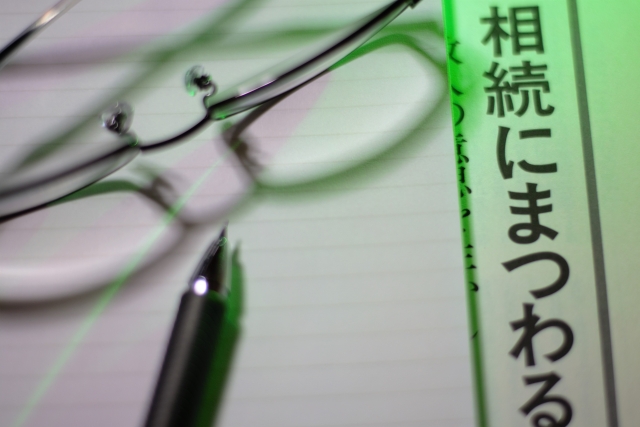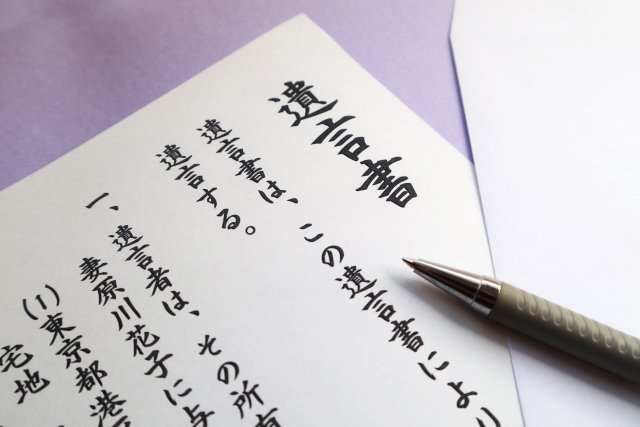相続・遺言・遺産分割について 新しい制度「家族信託」

「家族信託」の活用がいま注目されています・
家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
- 元気な時に親(委託者)の財産
- 子(受託者)に託す
- 親(委託者兼受託者)のために
- 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
- 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
- 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
- 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
- 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
👉今後のために遺言書を残しておきたい!
・子がいないから誰に残せばいいのだろうか(夫婦だけ)
・兄弟、姉妹の数が多い将来揉めなければいいが。。。(子供が大勢いる)
・配偶者、子が行方不明(家出していて戻ってきていないが)
・障害のある家族がいる(病気や障害のある子を残して)
・内縁関係中である(籍を入れていない)
・今の妻の子と離婚した妻との間の子がいる
・認知した子供がいる(認知したい)(昔いろいろとあった)
・特定の者だけに相続させたい(廃除したい者もいる)
法務省ホームページ 自筆証書遺言保管制度
改正相続法
近年の改正相続法のポイント(抜粋)※このHPの最近の記事(投稿)をご覧ください。
❶法務局での遺言書の保管(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言を作成したら、その遺言を法務局に保管してもらえます。改正前は、自筆証書遺言は自宅等に保管するしかなく、紛失、隠匿や、相続人が遺言に気づかないという可能性もありました。改正によって法務局に保管することができ安心となります。相続人が法務局に請求することで、遺言が保管されているか、どのような内容かを確認することができ、遺族が遺言書を見つけられないとう事態を回避できます。さらに、この制度の利用によりか家庭裁判所の検認が不要となりました。
❷夫婦間での土地・建物の贈与(2019年7月1日施行)
婚姻して20年以上の夫婦間で、土地・建物などの遺贈・贈与があったときに、その分は遺産の持戻しとして計算しない。改正前は、遺贈・贈与で土地・建物などを配偶者に渡しても、相続では遺産の持戻しとして計算され、結果として配偶者の取得額が増えるわけではありませんでしたが、改正により、居住用の土地・建物を配偶者へ遺贈・贈与した場合は、そのまま配偶者のものとなり、結果として配偶者の遺産の取得額が増えるようになります。※持戻し免除
❸配偶者居住権(2020年4月1日施行)
被相続人の建物に配偶者が住んでいる場合、配偶者は遺産分割で「配偶者居住権」というものを取得できるようになりました。改正により、その配偶者が建物の所有権を相続しなくても、原則、終身の間、無償で居住し続けることができる権利です。この権利、遺言、遺産分割、または家庭裁判所の裁定により設定さていなければならず。 相続した所有者は、配偶者居住権の設定登記する義務があります。建物は他の相続人が相続し、配偶者は配偶者居住権を取得することで、家に住み続けながら他の財産も受け取れるようになりました。
❹配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)
相続開始時に配偶者が被相続人の所有していた建物に居住していた場合、最低でも6ヶ月間はその家に無償で住み続けることができるようになりました。改正前は誰かに建物が遺贈されたり、被相続人が建物を使わせない遺言を残していたり、相続放棄したりすると、配偶者はそれまで住んでいた建物に住むことができないということになりますが、改正により、常に必ず6ヶ月間は配偶者が居住できるので、突然住む場所を失ってしまうことはありません。
❺預貯金の払い戻し(2019年7月1日施行)
被相続人の預貯金について、一定額までは家庭裁判所の許可を得ずに払い戻しを受けられるようになります。改正前は、原則、遺産分割が完了するか、家庭裁判所の許可を得ないと、葬儀費用や生活費として使う場合でも預貯金の払い戻しはできませんでした。
❻自筆証書遺言方式の変更(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書、押印が必要ですが、改正により、「財産目録」については、第三者がパソコンで作成しても、預金通帳などのコピーでも可能になりました。(財産目録の各ページに署名・押印は必要)
※その他、遺留分制度の見直し、権利取得の対抗要件の見直し、相続債権者の立場の明確化、相続人以外の者の貢献考慮など
相続・遺言・遺産分割
- 自筆遺言書作成サポート(お客様のニーズに適合した原案の作成アドバイス)
- 公正証書遺言書作成サポート(原案の作成、公証人との打ち合わせ、証人手配など)
- 戸籍調査、相続人確定調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成、財産目録作成遺言執行まで
建設業の許可をとろう!
工事を請け負うのに必須だよ。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う者
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)
(元請・下請、法人・個人を問いません)
個人でも大丈夫。
また、建設業は29業種に分類されており、業種
ごとに許可を受ける必要があります。
それぞれに要件がありそれをを満たす必要があります。
(メリット)
この許可を取得することにより、信用力がますますあがります。
逆に、無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられるのも事実です。
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。(これ未満だと軽微な工事となります)
【建設業許可要件】~5つの要件~
建設業許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
これら、要件をクリアできれば、晴れて建設業許可が取得できます。要件に該当するかどうかについては、細かく規定があるので、該当すると思っていてもダメな場合も多いので、よくよく準備確認をして申請をせねばなりません。