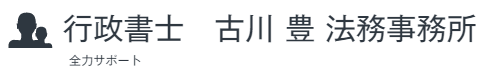画面サイズ毎の改行指定
画面サイズ毎の改行
xs サイズで改行されます。
画面サイズ毎の改行
sm サイズで改行されます。
画面サイズ毎の改行
md サイズで改行されます。
画面サイズ毎の改行
lg サイズで改行されます。
画面サイズ毎の改行
xl サイズで改行されます。
画面サイズ毎の改行
xxl サイズで改行されます。
背景塗り 灰色
二重線 上下線 黒
二重線 下線 黒
直線 上下線 黒
直線 下線 黒
点線 下線 黒
左右線
括弧 黒
リストブロック
- リストアイコン 矢印
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 三角
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン チェック
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン チェック 四角
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン チェック 丸
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 指
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 鉛筆
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 笑顔
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 不満顔
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 数字 丸
- アイコンの色は変更可能です。
- リストアイコン 数字 四角
- アイコンの色は変更可能です。
グループブロック
線の色、背景色は変更可能です。
※線の色は指定色にしか変更できません。
直線
直線角丸
直線 上下
点線
Dashed
二重線
二重線
画像ブロック










組み合わせ例

見出しブロック
- リストブロックの項目
- リストブロックの項目
- リストブロックの項目
- リストブロックの項目
非表示制御
非表示 画面サイズ Extra Small
非表示 画面サイズ Small
非表示 画面サイズ Medium
非表示 画面サイズ Large
非表示 画面サイズ Extra Large
家族信託(認知症になる前に!!)
家族信託とは
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々
家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもや配偶者などに渡すことができる契約です。
委託者:信託する人
受託者:財産の管理運用処分を任される人
受益者:財産から利益を受ける人(委託者と同じ場合がほとんど)
万が一親に認知症などが発症した場合でも、その影響を受けずに、配偶者や子どもなど(受託者)が信託財産の管理運用処分ができます。
親が認知症になったら。。。
対策をとっていないと
・預貯金の引出し、振込が本人でないとできない
・介護施設等入所の費用にあてようとした場合でも不動産(自宅等)が売れない
・財産に老朽化したアパートがあるけど、修繕も立替もできない
・銀行からの融資も受けれない
そこで、対策として
① 元気な時に親(委託者)の財産
② 子(受託者)に託す
③ 親(委託者兼受託者)のために
④ 子(受託者)が管理・運用・処分を
例えば不動産であれば、信託財産として名義だけ子(受託者)に移して、その信託財産からの実益は、親(受益者)のまま。
親が急に認知症になっても、受託者が管理、運営、処分ができるので安心
預金も信託口座口であれば、凍結されず、引出しできる
このような方はご検討ください。
1. 一人暮らしの親御さんの実家の管理をどうするか検討中
2. 親御さんがアパートのオーナーの場合で親御さん高齢になってきたので
3. 相続で子供が複数人いる場合に共有トラブルを回避したい場合
4. 事業承継(相続後の会社経営トラブル)をうまくやりたい
等々