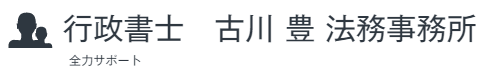農地転用・開発許可について
👉分家住宅を建てたい!
👉太陽光パネルを設置したい!
👉駐車場と資材置き場を作りたい!
土地活用を考えていらっしゃる方で、その土地が農地であれば「農地法」の適用を受けることになり、勝手に転用はできません。許可、届出の対象となり下記の申請書、添付書類を提出して申請することになります。
転用手続きには、下記申請書及び添付書類が必要です。弊事務所では、作成収集〜申請までのサポートを行います。
(業務範囲外については他士業と共同にて行います)
農地法第3・4・5条申請添付書類※個人の場合(地域により異なることがあります)
◎印は必須書類
○印は必要に応じて
| 必要書類名 | 3条 | 4条 | 5条 | 備考 | |
| 1 | 申請書 | ◎ | ◎ | ◎ | 3条は1部、4・5条は原本1部、写し1部提出。 |
| 2 | 地元農業委員・地元農地利用最適化推進委員確認書 | ◎ | ◎ | ◎ | 地元農業委員・地元農地利用最適化推進委員が申請内容及び現地を確認 |
| 3 | 土地の登記簿謄本(登記事項証明書) | ◎ | ◎ | ◎ | 申請日3ヶ月以内の原本。(法務局) |
| 4 | 字図 | ◎ | ◎ | ◎ | 申請地を示すこと。隣接地の地目・所有者記入。 |
| 5 | 位置図 | ◎ | ◎ | ◎ | 住宅地図等、現在の状況がわかる図。 |
| 6 | 現況写真 | ◎ | ◎ | ◎ | 申請地の現在の状況がわかる写真 |
| 7 | 申請地の平面図(土地利用計画図) | ◎ | ◎ | 排水経路等を記入し土地利用の目的を明確に。 | |
| 8 | 申請地の断面図 | ◎ | ◎ | 構造物や排水が分かるように。 | |
| 9 | 建物又は施設の平面図 | ◎ | ◎ | 建築面積等を記入。 | |
| 10 | 建物又は施設の立面図 | ◎ | ◎ | 構造物がある場合必要。 | |
| 11 | 承諾書 | ◎ | ◎ | 隣接耕作者。里道、水路管理者(区長等) | |
| 12 | 確約書 | ◎ | 耕作目的での農地取得の場合。(貸借を含む) | ||
| 13 | 工事見積書 | ◎ | ◎ | 消費税を含む金額を記載。有効期限内のもの。 | |
| 14 | 選定理由書 | ○ | ○ | 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域以外の農地は必要。 | |
| 15 | 資金証明書(残高又は融資) | ◎ | ◎ | 証明年月日は申請月の日付であること。ただし、申請が締切日から末日までの場合は、翌月の証明とする。原則原本を提出。通帳の写し可(申請者分に限る)。 | |
| 16 | 住民票 | ○ | ○ | ○ | 市外に居住している場合。 |
| 17 | 戸籍の附票 | ○ | ○ | ○ | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合。 |
| 18 | 求積図 | ○ | ○ | 一筆の一部を分筆せず一時転用等する場合。 | |
| 19 | 始末書及び現況写真 | ○ | ○ | 無断転用の場合、始末書は自署で押印し、写真は全景で撮影方向を配置図に記す | |
| 20 | 事業計画書 | ○ | ○ | ○ | 必要に応じて添付。 |
| 21 | 事業計画書(資材置場・駐車場) | ○ | ○ | 各資材置場及び駐車場ごとの利用状況を記載すること。 | |
| 22 | 過去の宅地・建売分譲の進捗状況 | ○ | ○ | 過去 3 年間の市内の農地転用許可分。 | |
| 23 | 借入金返済計画書 | ○ | ○ | ||
| 24 | 水利権者の同意書 | ○ | ○ | 取水、排水について同意を要する場合。 | |
| 25 | 仮登記権者の同意書 | ○ | ○ | ○ | 仮登記権が設定されている場合。譲受人の場合不要。 |
| 26 | 土地改良区の意見書 | ○ | ○ | 土地改良区域内にある場合。 | |
| 27 | 通行承諾書 | ○ | ○ | 申請地へ行くため他人の土地を利用する場合。 | |
| 28 | 他法令許認可申請書の写し | ○ | ○ | 関係機関の受付印があるもの。 | |
| 29 | 法人の定款又は寄付行為の写し | ||||
| 30 | 法人の登記簿謄本 | 申請日3ヶ月以内の原本。 | |||
| 31 | 宅地建物取引業免許証の写し | ○ | ○ | 建売分譲住宅、宅地分譲である場合。 | |
| 32 | 耕作者の同意書又は農地法第 18 条第 6 項による合意解約書の写し | ○ | ○ | ○ | 賃借権等に基づく耕作者がいる場合。 |
| 33 | 総会の議事録 | ○ | ○ | 法人格のない団体が申請する場合。 | |
| 34 | 地縁団体台帳 | ○ | ○ | ○ | 地縁団体の場合。 |
| 35 | 農地復元確約書 | ○ | ○ | 一時転用の場合。 | |
| 36 | 貸駐車場予定者名簿 | ○ | ○ | 駐車場台数の概ね7割以上。 | |
| 37 | 賃貸契約書(写) | ○ | 必要に応じて添付。 | ||
| 38 | 組合員名簿又は株主名簿の写し | 農地所有適格法人で、法人形態が農事組合法人又は株式会社の場合。 |
●農地法
農地は耕作者自身が所有することを最も適当と認めて,耕作者の農地取得促進,権利保護と土地の利用関係の調整によって,耕作者の地位の安定と生産力増進をはかることを目的とする法律です。日本では食料自給率確保のために簡単に農地を転用するために様々な条件があります。また農地とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。注意点として、登記簿上の地目または、事実状態で判断されます。
農地法に対する違反が発覚した場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の適用があり(農地法92条)、また転用工事の中止命令などが出されることもあります。
使っていない農地の有効活用(分家住宅、太陽光パネルの設置、駐車場、資材置き場など)
3条許可 農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可
4条許可 農地を農地以外のものにする場合の許可(田畑から雑種地へ変更するなど)
- 自己所有の有休農地があるから太陽光パネルを一面に敷き詰めて売電したいという場合

5条許可 農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)
- 高齢で農作業を一人で続けるのは難しいため、自分の子供に近くに家を建てて住んでもらって農業を継いでもらいたい、という場合には「分家住宅」を建てることが考えられます。この際、所有している農地の一部を住宅地にするために変更します。
農地転用の手続
都市計画区域内の農地を転用する場合
都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域に分けられています。そのため手続きも異なっています。
| 市街化区域 | 農地法上の農地転用の許可は不要⇒但し、農業委員会への届出は必要 |
| 市街化調整区域 | 同区域内の農地は、農地転用許可が必要 ⇒但し、同区域内は農振法の農用地区域に設定されている場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可になります。 |
農用地区域内の農地を転用する場合
農用地区域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、市町村が農業振興地域整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定めているものです。
このため、農地法における同区域内の農地転用は、一定の限られたものを除き、原則不許可となっています。
また、農用地区域内の開発行為に対しても、規制されています。
ただ、一定の要件を満たす場合には、転用しようとする農地に対して農用地区域からの除外申請を行い、除外してもらうことが可能になります。
つまり、農用地区域内の農地を転用するには、まず農用地区域から当該農地を除外してもらったうえで、農地法による転用許可を得る必要があります。除外の手続きには長期間(提出期限より概ね4~5ケ月)を要します。※申請時期には注意が必要
入国管理局申請取次行政書士に依頼しよう!
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
【申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請】
・在留資格認定証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
・資格外活動の許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
・在留資格の変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
・在留期間の更新許可申請
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
・在留資格の取得許可申請
(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OR RESIDENCE)
・永住許可申請
(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
・再入国の許可申請
(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
・就労資格証明書の交付申請
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
※帰化申請(外国人が日本国籍を取得するための申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。